以下のPDFファイルは、無料でダウンロードできます。
認定CM資格
 林桂大さん
林桂大さん大手ゼネコン会社/営業業務に従事/30代
建設工程の全体を知るために営業職から挑戦、
『CMガイドブック』と「CMガイドブック集中講座」で本質を掴んだ
事務系職種から認定CM資格にチャレンジし、見事合格を果たした林さん。営業職で担当した案件ではPM業務を経験し、さらに建設プロジェクト全体を把握するCM業務に関心を持ったといいます。直接的なCM経験がないまま【知識試験】【能力試験】にどう対応したのか、詳しい勉強法をお聞きしました。
建設プロジェクトの「基本」をちゃんと知りたい
営業職でも通常の営業活動に加えて受注前から構想を練り、社内関係部門と連携しながら設計業務や建設工程を検討するなど、PM関連業務も担当します。しかしコロナ禍になってお客様への訪問が全くできなくなってしまい、そのとき「自主的にいろいろ活動してみよう」と思って友人から教えてもらったのが認定CM資格試験の存在です。現場事務の経験から建物ができる過程は何となく理解していたんですが、ド標準といえる基本プロセスや仕組みがどういったものなのかはよく知りません。この試験からもっと勉強できるのではと思いました。
CM協会が提供する教材をひたすら繰り返した
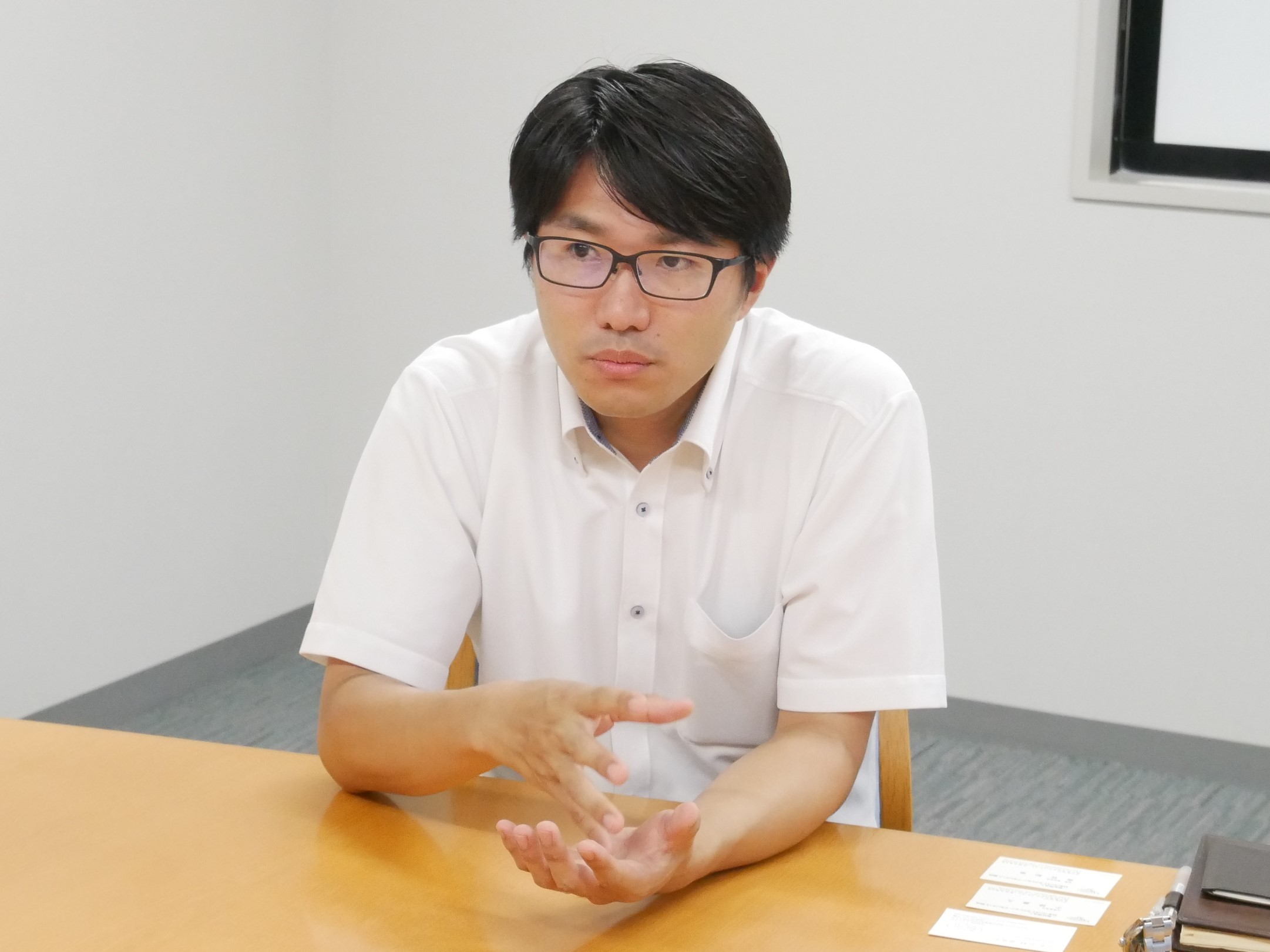 営業職の私の周りでこの試験を受ける人はなく、試験対策では『CMガイドブック』や「過去問」、「CMガイドブック集中講座」など協会が提供している教材をひたすら使いました。「集中講座」はオンデマンド受講が可能な「知識編」、リアルタイムのオンライン講座である「問題解決編」の両方を受けました。それ以外の勉強は特段していません。本当にこれだけです。
営業職の私の周りでこの試験を受ける人はなく、試験対策では『CMガイドブック』や「過去問」、「CMガイドブック集中講座」など協会が提供している教材をひたすら使いました。「集中講座」はオンデマンド受講が可能な「知識編」、リアルタイムのオンライン講座である「問題解決編」の両方を受けました。それ以外の勉強は特段していません。本当にこれだけです。
『ガイドブック』で良かったのは、プロジェクトの川上から川下まで、各フェーズについて時系列で章立てがなされていたことです。何も知らない最初のうちは冒頭からストーリーとして読み、勉強中も数え切れないほど通読しました。
何度も「過去問」を解いて分かったのは「本質は変わらない」という点です。CMにとって大切なのは「全体像を掴むこと」であり、プロジェクトの流れと「どのフェーズで何を求められるか」という基本さえ押さえれば仕事を理解できると感じました。
私は事務系なので一級建築士のような技術系の資格はありません。しかしCMとして工程を理解すれば、課題解決のために適切な技術者を選ぶことができ、協力して課題解決が可能になります。その役割を意識して全体像を掴んだ上で「次のステップへ円滑に進むにはどうするか」を考える。CM業務は行っていませんが、営業として担当する案件に置き換えて具体的にイメージしました。論述の展開では「過去問講評」で書かれていた指摘をヒントにしました。
技術系以外の分野でも、CCMJの知識が役立つ
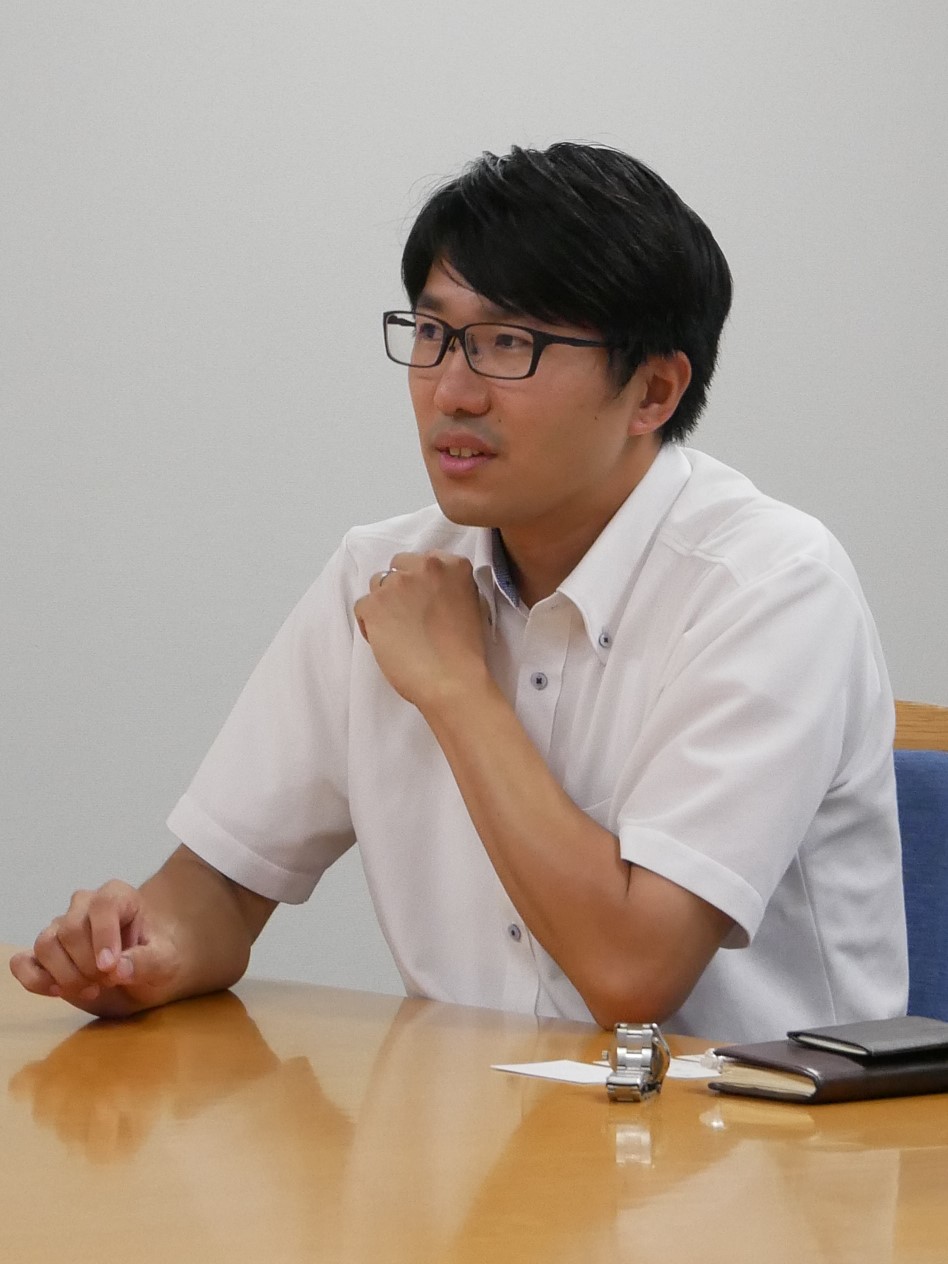 受験前は「専門知識のない自分は受けてもいいのか」と迷いました。しかし「集中講座・問題解決編」でリアルタイムに他の受験者の様子を見ると事務系なのは私だけ。その環境が面白く、かえって「受けてみよう」という気持ちになりました。
受験前は「専門知識のない自分は受けてもいいのか」と迷いました。しかし「集中講座・問題解決編」でリアルタイムに他の受験者の様子を見ると事務系なのは私だけ。その環境が面白く、かえって「受けてみよう」という気持ちになりました。
今は、技術系以外の方、建設プロジェクトに関わる方であれば誰でも早めにCCMJの勉強を始めていいのではと考えます。なぜなら、今まで点で捉えていた事柄が線としてつながり、自分が参画する工事で「今何をすればいいか」が明確になるからです。
私自身、工程の前後を知ることで先手を打てるようになり、技術者との会話を理解して進められるようになりました。実務を経験してからの勉強もいいんですが、新人のうちに全体を一度勉強し、後から実地で「これがあのことなのか」と理解を深めるのも大いに効果があると思います。ACCMJなら誰でも受験が可能なので、企業での資格取得支援が広がれば業界全体でメリットがあると感じました。
また、視野を広げるためにCM協会に入会して国際委員会に所属しています。自分が携わるプロジェクト以外でフランクに人と話せる機会はとても貴重です。新しい人の輪が広がるので、これからの人生が豊かになるのではと楽しみにしています。
 堀口大樹さん
堀口大樹さん建築設計会社/積算・コストマネジメント業務に従事/40代
「CM選奨」を読み込んで【能力試験】に対応、
実務経験が少なくてもCMrの立場を理解できた
大手ゼネコンで積算業務に携わった後、建設工程の上流にも関わりたいと考え建築設計会社に転職した堀口さん。コストマネジメントの視点から設計段階に参加した経験はあるものの、いわゆるCM業務の実務はほとんどなかったといいます。どのように【能力試験】を乗り越えたのかお聞きしました。
積算士の知識で「社内のCMr」として活動
コスト面から本当に貢献したいと思うと、出来上がった図面から見積書を起こす段階では何もできません。もっと上流のマネジメントや設計にも関わりたいと考えて、ゼネコンから建築設計会社へ転職しました。今は積算士の視点から社内でマネジメントを行う業務が増え、今後は外部でもマネジメント業務を提供できるように会社の体制が変わってきました。認定CM資格の取得は必要に迫られて取り組んだ感じです。
CM実務経験は少ないのですが【能力試験】の論述はよく書けたので「合格したな」と思っていたんです。しかし1回目は不合格。「何がダメだったんだろう」と考えて、新たに対策し直しました。
2回目の試験勉強、「CM選奨」から要点抽出
 不合格の原因として、まず思い当たったのは積算士の視点で考えすぎたことでした。与えられた課題に対して、コスト管理の面ではよく書けていたんですが視野が狭すぎる。CM業務で求められるスキルや思考は異なります。もっと全体像を俯瞰し、その上で「どんな問題点があるか、解決策が提示できるか」を探らなければいけない。大事なのはCMrの役割を理解することだと考えました。
不合格の原因として、まず思い当たったのは積算士の視点で考えすぎたことでした。与えられた課題に対して、コスト管理の面ではよく書けていたんですが視野が狭すぎる。CM業務で求められるスキルや思考は異なります。もっと全体像を俯瞰し、その上で「どんな問題点があるか、解決策が提示できるか」を探らなければいけない。大事なのはCMrの役割を理解することだと考えました。
進めるべき建設プロセスについてCMrの立場や役割をよく考えることが重要で、そこを掴めば解答となる論述が書けそうです。私の場合、業務でのCM経験は少ないので資料から要点を掴もうと考えました。このときに活用したのが日本CM協会が提供する「過去のCM選奨」データと、国土交通省が提供する「CM方式活用事例集」データです。
これらの資料はA4サイズ1枚に1物件の要点がまとめられています。1つ1つ読みながら、CMrが果たしている役割は何かを自分なりに考えて要点を書き出しました。通して読み込むと「CMとしてクリアしなければいけない部分はここか」「こういう点が問われるのかな」と共通項がイメージできます。論述ではそれを踏まえ、「CMrがどんな立場で、どんな役割を果たさなければいけないのか」を意識して書くようにしました。
勉強して「立場を理解した」こと自体に価値がある
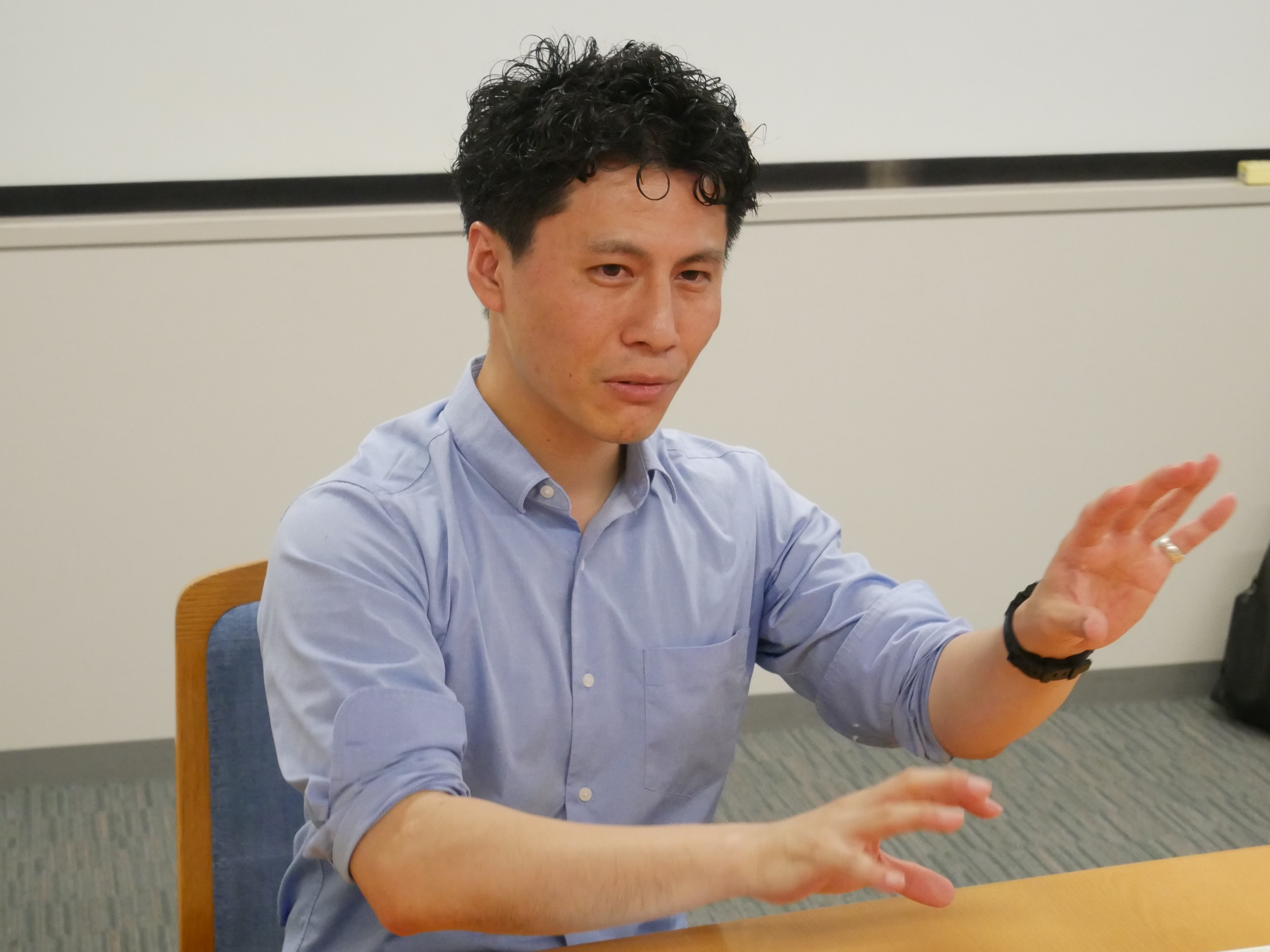 2回目の受験に向けて、日常業務でも「CMrだったらこうするだろう」というアンテナが結構立ったので、その思考も合格につながったかもしれません。「認定CM資格試験として書いてほしい内容」を知るために、2回目は「過去問講評」も読み込みました。『CMガイドブック』は、まだ仕事で使っていない用語の確認で参考になります。実際の業務で専門用語に出合っても、試験対策で覚えていてスムーズに会話が進んだこともありました。
2回目の受験に向けて、日常業務でも「CMrだったらこうするだろう」というアンテナが結構立ったので、その思考も合格につながったかもしれません。「認定CM資格試験として書いてほしい内容」を知るために、2回目は「過去問講評」も読み込みました。『CMガイドブック』は、まだ仕事で使っていない用語の確認で参考になります。実際の業務で専門用語に出合っても、試験対策で覚えていてスムーズに会話が進んだこともありました。
試験勉強の一番の成果は「CMrの立場を理解したこと」だと思います。設計やコストマネジメントの立場でプロジェクトに参加したときも、外部からCMrが参加しているケースが結構あるんです。なぜそうするのか、以前より彼らの立場や役割をより詳しく理解できるようになったのは大きいですね。極端にいえば、合否とは別に「CMの勉強ができたこと自体」にかなりの価値を感じています。
積算士の視点なら「こうすればいい」と簡単にいえることでも、CMr視点を得て発注者の立場を考慮すると解決法が変わりますし、さまざまなアイデアを吟味する発想が生まれます。中立的立場や説明責任に伴う振る舞いもCMの勉強から意識するようになったので、今回受験してよかったです。
 宇賀那果林さん
宇賀那果林さんCM専業企業/CM業務に従事/30代
「この課題は、どう解決してどう説明する?」
日常のCM業務で【能力問題】の記述力を鍛えた
前職で内装設計を経験し、現在はCMrとして業務に携わっている宇賀那さん。所属はCM専業企業のため、会社を挙げて認定CM資格取得に取り組んでいるそうです。2回目の挑戦で【能力試験】に合格したとのこと、どのような勉強で合格に至ったのかお聞きしました。
過去問を解き、『CMガイドブック』で確かめる
会社からの方針として「社員は認定CM資格をぜひ取得するように」と言われています。CM専業企業としてCM資格の取得は当然のことですし、また民間工事だけでなく公共事業に携わる機会もあり、資格取得者を増やすために力を入れているのだと思います。そのぶん社内では勉強会も開催されますし、合格した先輩からコツやアドバイスを聞ける環境があるのはありがたいです。
先輩から最初に教わったのは「過去問を何度も解くこと」でした。まず自分で過去問を解き、間違えた項目は『CMガイドブック』で調べ、それを頭に叩き込む。『ガイドブック』はボリュームがあるので、通しで読むよりも「間違えたら確認する」のを何度も繰り返すほうが効率がよいと思います。本腰を入れたのは試験1カ月前でしたが【知識試験】はこれで合格できました。
2回目の【能力試験】だからこそ、成長を実感できた
 初めて認定CM資格試験を受けたのは転職して半年後の夏です。【知識試験】は受かったのですが、1回目の【能力試験】では落ちてしまいました。今から考えるとまだCMの実務経験が浅く、使えるボキャブラリーも少なくて力不足を痛感しました。そのときの出来る限りで記述しましたが、まだプロジェクトの全体像のようなものは掴めておらず、合格基準には達していなかったのだと思います。
初めて認定CM資格試験を受けたのは転職して半年後の夏です。【知識試験】は受かったのですが、1回目の【能力試験】では落ちてしまいました。今から考えるとまだCMの実務経験が浅く、使えるボキャブラリーも少なくて力不足を痛感しました。そのときの出来る限りで記述しましたが、まだプロジェクトの全体像のようなものは掴めておらず、合格基準には達していなかったのだと思います。
2回目の【能力試験】に向けて一番の手がかりにしたのは、過去問の「解答講評」です。会社に蓄積されている過去問の講評を読み込み、「どう書いたら合格できるのか」を考えました。
会社の勉強会では「箇条書きでは書かないほうがよい」というアドバイスをいただきました。ある先輩は【能力試験】に箇条書きで解答して不合格が続いていたそうなのですが、ある年に文章で解答したら合格したという出来事がありました。確か、過去の講評にも「箇条書きで書く人が多い」と注意があったと思います。ここから、試験ではロジックの構築力が見られるのだと予測しました。
同時にとても役立ったのは日常のCM業務です。仕事を覚えて任される領域が広がるとさまざま壁にぶつかります。そのとき「この課題はどう解決しようか」と自分の頭で考え、乗り越えた経験が引き出しとなり、2回目の【能力試験】では論述を埋めることができました。「去年の私は全然書けなかったけれど、今年はここまで書けた」という達成感は、2回目ならではの経験かもしれません。「ちゃんと経験を積んできたんだ」という自信になりました。
CM職以外の皆さんにも役立つ資格
 実際のCM業務には正解がなく、常にいろんな立場で物事を考えて調整する役割が求められます。その力が【能力試験】で試されるように感じました。「この課題についてあなたはどう料理しますか」と問われて、関係者を説得できるロジックを組み立てられるかどうか。もちろんボキャブラリーについては専門知識が必要ですが、問われるのはテクニカルな知識ではなく、経験や考え方なのだと思います。
実際のCM業務には正解がなく、常にいろんな立場で物事を考えて調整する役割が求められます。その力が【能力試験】で試されるように感じました。「この課題についてあなたはどう料理しますか」と問われて、関係者を説得できるロジックを組み立てられるかどうか。もちろんボキャブラリーについては専門知識が必要ですが、問われるのはテクニカルな知識ではなく、経験や考え方なのだと思います。
また、受験してみて「これはCM職以外の方にも知ってほしい知識・資格」だと感じました。実際にCMrとして働く方だけでなく、CMを活用する側の皆さんにも認定CM資格の知識は役立ちます。建設プロジェクトの流れを上流から下流までまとめて学べる資格として、もっと広まればいいなと思っています。